ディーニーズ株式会社
ボイスボット注文受付で機会損失防止 人と遜色ない受注率83%で、クレジットカード決済完結
| 導入サービス | PKSHA VoiceAgent(ボイスボット) |
|---|---|
| 業種 | 小売・卸売・商社 |
| 活用対象 | お客様からの問い合わせ |
| 導入目的 | 顧客満足度向上, 業務効率化 |

ディーニーズ株式会社
業務本部 本部長 葛城 賢二様
業務本部テレマーケティング事業部 マネージャー 谷口 正洋様
業務本部テレマーケティング事業部 上野 俊太郎様
テレマーケティング事業部の役割とミッション
まず、貴社の事業内容とテレマーケティング事業部の役割についてお聞かせください。
弊社は、テレビ通販を中心とした通信販売事業を行っており、「青汁三昧」といった健康食品から、「ジニエブラ」などの補正下着、調理器具まで、お客様の生活を豊かにする商品を幅広く扱っています。
私たちの所属するテレマーケティング事業部は、テレビCMをご覧になった新規のお客様からのご注文や、お問合せの電話受付を担うコールセンターの運営・管理が主なミッションです。
お客様は60代から80代の方が中心で、インターネットよりも電話でのコミュニケーションを好まれる世代です。そのため、電話対応がメインとなっており、私たちが会社の顔としてお客様と直接向き合う重要な部署になります。
コールセンターの規模や業務内容について教えてください。
受注拠点は全部で5つあり、常時20名程度のオペレーターが対応していますが繁忙期は最大で100名体制になることもあります。繁閑の差が非常に激しいのが特徴です。
入電いただく方の8割は、ご注文、もしくは商品に付随する内容です。例えば、商品の金額や素材・用途など、購入前に聞いておきたいというお問い合わせですね。残りの2割が、ご注文後の変更やキャンセル、注文内容の確認、お届け日時の指定といった内容です。
テレマーケティング事業部のKPIは。
受注率やアップセル率といったKPIの管理に加え、売上や人件費、受注コストの管理も行っています。特に、入電予測に基づいた適切な人員配置は、収益に直結するため最も重要視している業務です。

あふれ呼による機会損失が大きな課題
ボイスボット導入前は、どのような課題を抱えていましたか。
導入前は、オペレーターが対応しきれずあふれてしまったコールをIVRで受け、後ほどかけ直す「コールバック」で対応していました。架電しても一度でお客様につながらない事が多いため、2度3度架電することになり、工数がかさんでしまいます。それでもコールバック対象のお客様のうち、15%はつながらずに受注の機会を逃していました。
また、コールバックでお客様につながったあとの受注率の低下も大きな問題でした。お客様からご注文のお電話をお受けした場合の受注率は約80%ですが、コールバックでは60~65%まで落ち込んでいました。数時間後にかけ直した時には、お客様の熱が冷めてしまったり、他で類似商品を購入してしまっていることがありました。
呼量予測に合わせた人員配置は難しかったのでしょうか。
もちろん予測は立てるのですが、テレビ通販の呼量は天候や突発的なニュースなど外部要因に大きく左右されるため、正確な予測は非常に困難でした。人員が不足すれば、お客様をお待たせしてしまい、機会損失や顧客満足度の低下に直結します。逆に人員を過剰に配置すれば、コスト増につながるジレンマがあります。
現場ではオペレーターの急な欠勤や採用難もあり、計画通りの人員を確保できないことも多く、基本的には人手が足りない状況でした。呼量予測が完全に正確にできない前提のもと、コールバック発信業務の抑制と機会損失防止のため、ボイスボットでの注文受付を開始しました。
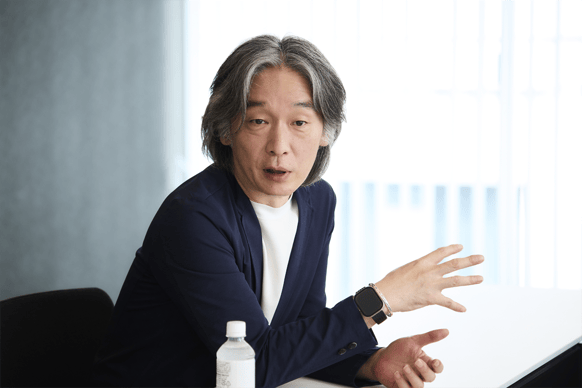
PKSHA VoiceAgentの注文受付で目覚ましい効果
現在、どのようにボイスボットを活用していますか。
2023年11月から、あふれ呼の一次対応を「PKSHA VoiceAgent」に切り替え、まずは代金引換の注文から自動化をスタートさせました。2025年5月からは、クレジットカード決済にもボイスボットで対応できるようにしました。
元々カスタマーサービスセンターで「PKSHA VoiceAgent」を利用していたため、注文受付での活用もスムーズに開始できました。
どのような効果がありましたか。
ボイスボットの導入により、接続率と受注率が改善されたことで売上も増加しています。
これまでは、ご注文のお電話に対してIVR経由のコールバック対応の比率30%程度だったところ、10%ポイントほど改善できています。ボイスボットのおかげであふれ呼にならなかった入電のうち、15% (コールバック対応の場合繋がらなくなってしまう割合) を機会損失から防げていることになります。
コールバック対応では60〜65%程度であった受注率が、ボイスボットでお待たせすることなく注文受付すると83%程度まで改善しています。これは、人が対応した場合の受注率である約80%とほぼ同等の数値です。
当社にとってのメリットも大きいですが、なにより、お客様をお待たせしていた状況を改善できたことが大きいと感じます。
他に良い影響はありましたか。
コールセンターの人員配置の柔軟性が上がりました。オペレーターの確保が特に難しい深夜や早朝の時間帯は特に効果が大きいと感じます。
例えば、深夜2時にテレビCMが流れる場合、その時間帯だけ稼働できるオペレーターを確保することは難しいですが、ボイスボットなら問題ありません。ボイスボットで注文を受け付ける前提で手配するオペレーターの人数を抑制する、という使い方をしています。
導入前に社内で懸念の声はありませんでしたか。
クレームを心配する声もありましたが、実際にはほとんどなく、お客様にもスムーズにご利用いただけています。カスタマーサービスセンターでの実績も安心材料でした。

機能性と自由度の高さで高速改善
導入やフロー構築において、工夫された点はありますか。
ボイスボットで注文受付を開始した当初は受注率が40%程度でしたが、そこから改善を重ねることで83%まで向上させることができました。
例えば、注文受付時にお客様の個人情報(お名前やご住所)は必要不可欠ですが、どうしてもボイスボットの精度は100%になりません。そこで、音声認識の正確性を上げるために当初はボイスボットに復唱確認をさせていたのですが、むしろ復唱確認でつまずいてしまい、注文受付が完了しないという問題がありました。
あえて完全に正確な個人情報をボイスボットで取得することはあきらめ、あとでオペレーターが録音を聞き直すフローに変更しました。この割り切りが、結果的に受注率を大きく向上させる転換点になりました。
他にも、お客様がなるべく悩まないように問いかける工夫をしています。「ご注文の商品は何ですか?」というような聞き方ではなく、「ご注文の商品は◯◯ですね?」のように、「はい」「いいえ」で回答できるようにしています。PKSHA VoiceAgentは「はい」「いいえ」を別の言い回しでもニュアンスを汲み取って認識してくれるので、とても効果的でした。
PKSHA VoiceAgentが便利だと感じたポイントはどこですか。
業務担当者である私たちが、専門知識なしで自由にフローを組み替え、すぐにテストできる点です。
業務を一番理解している担当者が、自ら高度なシステムを構築できる。これこそがSaaSの本質的な価値だと思います。他社製品ではベンダーに修正をお願いする必要があり、変更に時間がかかるシステムもあるようです。そのようなシステムでは、当初の受注率40%からなかなか改善させることができず、この取り組みは中止になっていたかもしれません。
使い勝手が良いと感じる機能は何ですか。
簡易データベース機能と条件分岐機能が非常に便利で、この2つを使いこなせば、かなり複雑な注文やお問い合わせにも対応できると思います。例えば、お客様が選択した商品の色やサイズ、お客様のご住所に応じて、復唱する商品名や送料を動的に変更しています。
ほかにも、ご注文時にお客様在住の「都道府県」と「入電時間」からテレビCMを特定し、自動的に注文と紐づけることで、媒体の成果分析に活かすことができています。
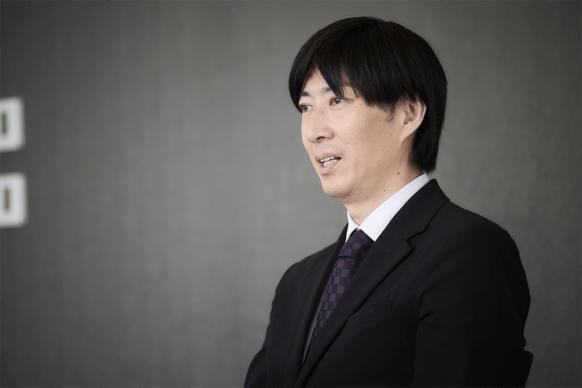
100%自動化を目指し、まずは「やってみる」の精神
ボイスボットやAIの今後の活用方針は。
理想は、受注の100%自動化です。現在は特定の放送枠や商品での運用ですが、今後はさらに対応範囲を広げていきたいです。また、より複雑な問い合わせが多いカスタマーサポートの領域でも活用を広げ、事業全体の生産性を高めていきたいと考えています。
少子高齢化による人材不足は、今後さらに深刻になります。災害やパンデミックといった不測の事態でも事業を継続できるよう、今のうちから自動化できる業務は積極的にシステムに任せていくべきだと考えています。
最後に、導入を検討している方へメッセージをお願いします。
最初から完璧なものを目指すのではなく、まずは「やってみる」ことが何よりも大切だと思います。実際にやってみなければ、本当の課題は見えてきませんし、改善のサイクルも始まりません。できることからスモールスタートで始めて、少しずつ改善を重ねていくことが成功への近道だと思います。
「どうやるか」を考えすぎて動けなくなるのではなく、まずは「やってみる」という姿勢が重要です。きっと、想像以上の成果が得られるはずです。